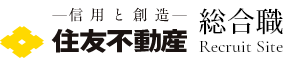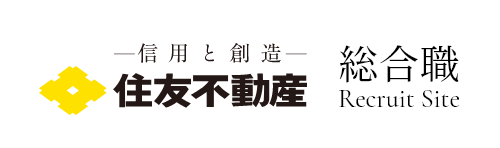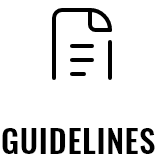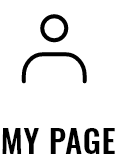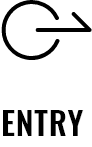“普通”は通用しない。10年経験しても飽き足りない、住友不動産らしい開発とは。“普通”は通用しない。10年経験しても飽き足りない、住友不動産らしい開発とは。
住宅分譲事業本部
阿蘇 章剛 2009年入社
※所属は取材当時のものです。
PROFILE
法学部卒業。就活時に注目していたのは、生活に身近なビジネス。その一つとして、不動産業界に出会う。中でも、大きな組織の一員として決められた仕事だけをするより、少数精鋭の組織で幅広い仕事に挑戦できる環境に興味を持つ。有名メーカーやメガバンク、大手デベロッパー各社の選考を受けた末、住友不動産に入社を決意。入社2年目から用地仕入の部門に所属。現在は課長として管理業務も担う。プライベートでは2児の父親。

新しくつくる、だけでなく。
残す、も考える開発者でありたい。
入社6年目の頃、ある土地を400年以上所有していた地権者様との出会いがありました。駅前の180坪ほどの大きな土地は、隣りの地所を所有していた当社としてはぜひ譲っていただきたい土地でした。ですが、地権者様であるご夫婦にとっては、江戸時代から代々受け継いできた大切なもの。ご子息に残していきたいとお考えでした。
私はあらゆる提案をしました。当社が土地を買い取る案だけでなく、同じ価値の不動産を譲渡する代替の案や、その地に完成する建物の一部の所有権を引き渡す等価交換の案など。ですが、ご夫婦の想いは変わりませんでした。
そこで私は、より良い継承の方法をお二人と一緒に考えることに。理想的な資産の残し方とは何だろうか。地権者様の立場で考え、悩んだ結果、他の多くの案件のように土地の所有権を当社に譲っていただくのではなく、一部の所有権は地権者様のまま、当社に貸していただくという案を提案しました。ご子息に確かに残していくことを重視していたお二人にも、これなら安心してもらえるだろうと思ったのです。その土地のビルの屋上の隅に位置していたお稲荷様についても、残し方をとことん考えました。それは、かつてご一家が商店を営み、地域の繁栄に寄与した証。前例はあまりありませんが、新たにできるビルの入り口前への引っ越しをご提案しました。ただ残すのではなく、もっと地域にとって身近な存在になったらいいなと思ったのです。最終的に土地を任せていただけたのは、他社にないその提案も含め、地権者様に寄り添う姿勢を評価してもらえたからだと思います。
私たちの仕事は、地権者様や地域にとって大切なものや想いを未来に繋いでいく方法を考えることでもある。この案件からの学びは、今も私にとって大切な心得になっています。

もっと他にできることはないのか?
経営層から常に問われる環境。
私たち開発者の仕事に対して、華やかな仕事だと感じる人も多いかもしれません。でも実際は、すごく地道で泥臭い仕事です。その土地をどう活かすのか、地権者様や街の発展のためになるプランを考えるのは当然のこと。そのうえで、利益を最大化しなければならない。ビジネスですから。そのためのあらゆる工夫を尽くすことが求められます。たとえば、少しでも広い土地にできるよう、地権者様を一人ひとり口説いて回るのもそう。その土地を最大限有効活用できるように開発手法を検討する、プロジェクトの収支を細かくコントロールする、何より1日でも早く収益化できるよう工事スケジュールを綿密に管理する、といったこともそう。「利益最大化」と言えばクールかもしれませんが、小さな努力の積み重ねなのです。
当社ではその努力について常日頃問われます。社長や副社長へ直接プレゼンする機会が多いのですが、その際には必ずと言ってよいほど「開発者として考えているか?」「もっと他にできることはないのか?」と。入社から10年以上経つ今も、指摘を受ける日々です。「こんなものだろう」はどんな場面でも許されない。仕事の進め方も、仕組みも、日々見直すことが求められる。正直、厳しい環境です。でも、だからこそ当社は、業界の常識を覆すようなアイデアを数々実現させてきたのです。
入社した当時の私は、「将来、注目度の高いプロジェクトに携わりたい」と思っていました。ある意味、受け身だったのです。しかし今は、そうではありません。「自分の仕事を話題性のあるものにしてみせる」という気概を持ち、住友不動産らしい開発をこれからも追求し続けていきます。